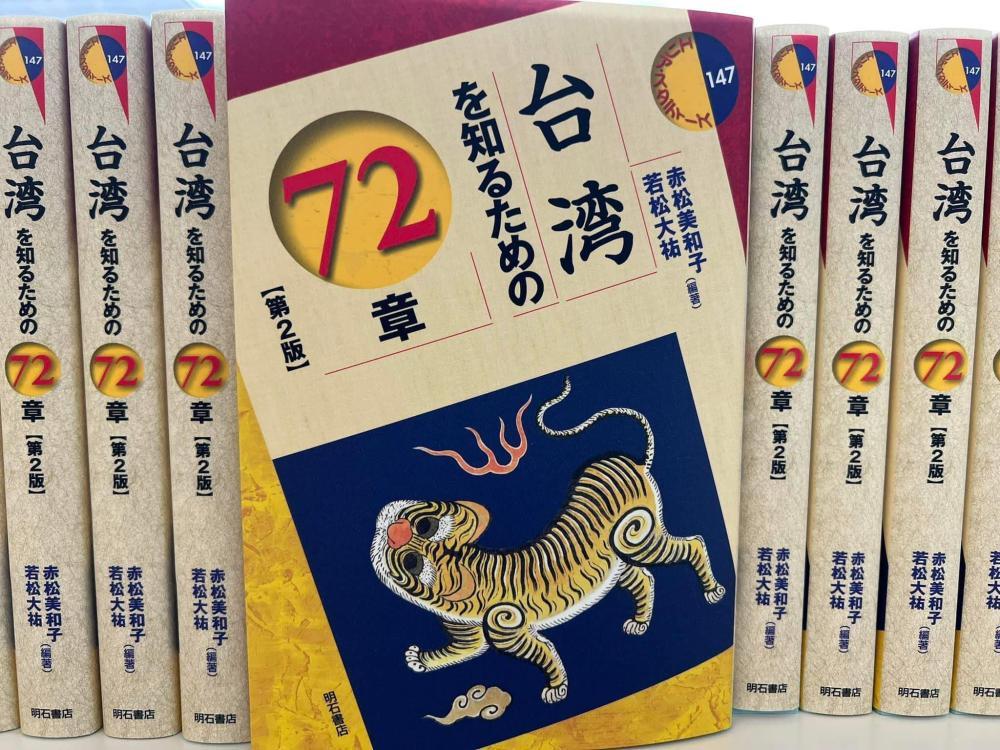【台湾を知るための72章(第2版)】
赤松 美和子 編著
若松 大祐 編著
====
内容説明
現在、国際社会においてその存在感を増す一方で、地域情勢の変動で耳目を集める台湾。本書は旧版をバージョンアップし、この地に関する基本的な知識を提供するとともに、最新の情報を盛り込む、台湾入門書である。
====
【書評情報・関連記事】
○断交後50年の友好国「台湾」の現在・過去を知り、未来を読み解く『台湾を知るための72章 第2版』(じんぶん堂)
====
【執筆者一覧】
赤松美和子(あかまつ・みわこ) ※編著者紹介を参照
大妻女子大学比較文化学部准教授
『台湾文学と文学キャンプ』東方書店、2012年。
家永真幸(いえなが・まさき)
東京女子大学現代教養学部准教授
『国宝の政治史──「中国」の故宮とパンダ』東京大学出版会、2017年。
稲見公仁子(いなみ・くにこ)
台湾影視研究所主宰
(共著)『アジア映画の森 新世紀の映画地図』作品社、2012年。
王智明(おう・ちめい)
中央研究院欧米研究所副研究員
『落地転訳:台湾外文研究的百年軌跡』聯経:2021。
王韶君(おう・しょうくん)
財団法人鄭南榕基金会特任研究員
『日治時期「中國」作為工具的台湾身分思索:以謝雪漁、李逸濤、魏清徳為研究対象』,台北:稲郷出版社、2019年。
大岡響子(おおおか・きょうこ)
国際基督教大学アジア文化研究所研究員
「芦田恵之助の回想録と日記の比較から見る台湾表象と「国語」教育観」、田中祐介編『無数のひとりが紡ぐ歴史』文学通信、2022年。
大川謙作(おおかわ・けんさく)
日本大学文理学部教授
“Latent Modernization in Traditional Tibet: ”,Revue d’Etudes Tibétaines, vol. 57, 2021.
岡﨑滋樹(おかざき・しげき)
松本大学総合経営学部講師
「日中戦争期の台湾拓殖株式会社による海南島畜産事業」『東洋学報』第103巻第2号、2021年9月。
岡野翔太(葉翔太)(おかの・しょうた)
大阪大学大学院言語文化研究科特任研究員
「華僑から『台湾人』へ」、林初梅・所澤潤・石井清輝編『二つの時代を生きた台湾』三元社、2021年。
金丸裕一(かねまる・ゆういち
立命館大学経済学部教授
「黒田四郎『南京回想』の探究──戦時日中キリスト教関係史をめぐる実証研究」、『キリスト教史学』第75集、2021年。
上村泰裕(かみむら・やすひろ)
名古屋大学環境学研究科准教授
『福祉のアジア─国際比較から政策構想へ』名古屋大学出版会、2015年。
北波道子(きたば・みちこ)
関西大学経済学部教授
「台湾の経済発展と「開発独裁」」陳來幸・北波道子・岡野翔太編『交錯する台湾認識』勉誠出版、2016年。
木村自(きむら・みずか)
立教大学社会学部准教授
『雲南ムスリム・ディアスポラの民族誌』風響社、2016年。
呉孟晋(くれ・もとゆき)
京都大学人文科学研究所准教授
『京都国立博物館須磨コレクション図版目録:中国近代絵画1斉白石』中央公論美術出版、2019年。
黒羽夏彦(くろは・なつひこ)
国立成功大学歴史学研究所博士課程
「領台当初における『九州日日新聞』の台湾報道」、『近代東アジアと日本文化』銀河書籍、2021年。
胡欣立(こ・きんりつ)
香港恒生大学助理教授
從《反分裂國家法》到《國家安全法》涉港澳台部分的立法觀察,《亞洲研究》,第75期,珠海學院亞洲研究中心,2019。
黄偉修(こう・いしゅう)
東京大学東洋文化研究所助教
『李登輝政権の大陸政策決定過程(1996-2000年)──組織的決定と独断の相克』大学教育出版、2012年2月。
洪郁如(こう・いくじょ)
一橋大学大学院社会学研究科教授
『誰の日本時代:ジェンダー・階層・帝国の台湾史』法政大学出版局、2021年。
菅野敦志(すがの・あつし)
共立女子大学国際学部准教授
『台湾の国家と文化──「脱日本化」・「中国化」・「本土化」』勁草書房、2011年。
栖来ひかり(すみき・ひかり)
クラブ光
『時をかける台湾Y字路──記憶のワンダーランドへようこそ』図書出版ヘウレーカ、2019年。
関谷元子(せきや・もとこ)
音楽評論家、国士舘大学非常勤講師
『POPASIAポップ・アジア』編集長
薛化元(せつ・かげん)
国立政治大学台湾史研究所教授
『民主的浪漫之路──雷震伝』遠流、2020年。
高橋孝治(たかはし・こうじ)
一般企業勤務、立教大学特任研究員
『中国社会の法社会学──「無秩序」の奥にある法則の探求』明石書店、2019年。
田上智宜(たのうえ・ともよし)
熊本学園大学外国語学部准教授
「客家基本法からみるエスニシティ概念の変化」『アジア地域文化研究』第7号、2011年。
田畠真弓(たばた・まゆみ)
専修大学商学部教授
“The Risk of Upgrading Strategy”, Journal of Asian Sociology, Vol. 50, Num.1, 2021,pp. 117-142. (Indexed in SCOPUS)
張大鎮(ちょう・たいちん)
国立病院機構東京病院放射線診療センター医長
Stereotactic irradiation for intracranial arteriovenous malformation using stereotactic radiosurgery or hypofractionated stereotactic radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2004 Nov 1;60(3):861-70.
趙家緯(ちょう・かい)
台湾環境規画協会理事長
2020, with Kuei-Tien Chou, “Governing the Climate-Driven Systemic Risk in Taiwan” in Climate Change Governance in Asia, NewYork: Routledge.
陳威志(ちん・いし、(台)ダン・ウィジ)
地球公民基金会兼任研究員
「脱原発への態度」、町村敬志・佐藤圭一『脱原発をめざす市民活動』新曜社、2016年。
根岸忠(ねぎし・ただし)
高知県立大学文化学部准教授
「家事使用人の労働条件保護はどのようになされるべきか」、『日本労働法学会誌』133号、2020年。
原正人(はら・まさと)
中央大学法学部准教授
『近代中国の知識人とメディア、権力──研究系の行動と思想、1912-1929』研文出版、2012年。
福岡静哉(ふくおか・しずや)
毎日新聞外信部副部長
「新型コロナウイルスの封じ込めで増した台湾の存在感」『UP plus コロナ以後の東アジア』東京大学出版会、2020年。
松田良孝(まつだ・よしたか)
フリーランス、(元)八重山毎日新聞記者
『与那国台湾往来記「国境」に暮す人々』南山舎、2013年。
宮岡真央子(みやおか・まおこ)
福岡大学人文学部教授
「台湾山地先住民の村における新型コロナウイルス感染症のインパクト」、『アジア遊学253 ポストコロナ時代の東アジア』勉誠出版、2020年。
村上太輝夫(むらかみ・たきお)
朝日新聞社オピニオン編集部解説面編集長
「三・一一後の日台関係 台北からの光景」、『ワセダアジアレビュー』11号、2012年。
百瀬英樹(ももせ・ひでき)
世新大学日本語文学系講師
(共著)「ポピュラー文化の観光資源化と『伝統の創造』」、『仁愛大学研究紀要人間学部篇』14号、2015年。
山﨑直也(やまざき・なおや)
帝京大学外国語学部教授
『戦後台湾教育とナショナル・アイデンティティ』東信堂、2009年。
横田祥子(よこた・さちこ)
滋賀県立大学人間文化学研究院准教授
『家族を生み出す:台湾をめぐる国際結婚の民族誌』春風社、2021年。
劉夏如(りゅう・かじょ)
玉山社出版社AsiaRethink企画編集長
「慰安婦問題」、若林正丈・家永真幸『台湾研究入門』東京大学出版会、2020年。
劉靈均(りゅう・れいきん)
相模女子大学、関西大学非常勤講師
「日本語の『台湾同志文学』の誕生:李琴峰『独り舞』論」、『未名』33号、2019年。
林怡蕿(りん・いけん、リン・イーシェン)
立教大学社会学部教授
『台湾のエスニシティとメディア──統合の受容と拒絶のポリティクス』立教大学出版会、2014年。
若松大祐(わかまつ・だいすけ) ※編著者紹介を参照
常葉大学外国語学部准教授
「アジアの孤児と異域の孤軍」、内田隆三『現代社会と人間への問い』せりか書房、2015年。
渡邉義孝(わたなべ・よしたか)
尾道市立大学非常勤講師
『台湾日式建築紀行』時報出版社、2019年。
====
目次
はじめに――50年間も国交のないままの友好国を知る
Ⅰ 現在までの歩み
第0章 新型コロナ対策の「優等生」――国際社会で増した台湾の存在感
【コラム1】暮らしの基本データ
第1章 地理・自然・先史――オーストロネシア語族と熱帯の島
第2章 オランダ時代・明鄭時代・清代――台湾島規模の統治領域の形成
第3章 日本統治時代――ほぼ台湾島規模での住民意識の登場
第4章 国民党統治時代――国際社会における台湾規模の行為主体の登場
第5章 憲法修正以降――中華民国と台湾との絡まる現状維持
第6章 台湾理解の変遷――外部の視点から台湾本位の「我々」の視点へ
第7章 日本統治時代の捉え方――台湾史の多元性から考える
Ⅱ 政治と経済
第8章 政治体制――五権分立の中華民国の主権と統治権
第9章 主権国家――統一・独立・現状維持
【コラム2】国立故宮博物院
第10章 政党と国家像――想定する空間的規模の異なる二大政党
第11章 台湾人アイデンティティと中国人アイデンティティ――台湾住民の帰属意識の歩み
第12章 憲法――「民主」への遠い道のり
第13章 法律――様々な要素を持つ台湾法の歩みと現在地
第14章 選挙――進化を続ける民主政治
第15章 移行期における正義――中華民国の所業に対する清算の試み
第16章 農業――主要産業から斜陽産業へ
第17章 工業――世界一のハイテク請負アイランド
第18章 経済発展――謎と奇跡の初期条件
第19章 インフラ――灌漑施設、発電所、高速道路、交通
第20章 金融・財政・税金――お金の流れからみる中華民国のかたち
第21章 国際経済――輸出志向工業化・金融自由化・国営企業民営化・WTO加盟
第22章 市民参画型の産業発展――助け合い精神が育むソーシャルビジネス
第23章 環境とエネルギー――非原子力からカーボンニュートラルへ
第24章 労働・就労――自分に合った仕事を求めて転職
【コラム3】出入国管理
第25章 観光――旅行が大好きな国のインバウンドとアウトバウンド
【コラム4】温泉
Ⅲ 社会
第26章 エスニック・グループ――省籍矛盾、四大族群、そして新住民
第27章 原住民/先住民――誇り高く生きる人々
第28章 閩南人(福佬人)――言葉と政治の多数派
第29章 客家人――少数派漢人の言語と伝統文化
第30章 外省人――タロイモさん・眷村・牛肉麵
第31章 チベット人とモンゴル人――現代に残る五族共和
第32章 新住民――中国や東南アジアからやってきた新しい台湾人
第33章 言語――共通語・母語・字体・表音式表記
第34章 建築――重層する歴史を示す都市景観
【コラム5】建築保存と民主主義
第35章 社会運動――第四原発反対運動・ひまわり学生運動をめぐる政党の駆け引き
第36章 ジェンダー――「アジアの優等生」の過去・現在・未来
第37章 性的少数派――同性婚合法化への道のり・終わらない闘い
第38章 教育制度――学歴社会は変われるか
第39章 大学――狭き門から大衆化の時代へ
第40章 日本語教育――125年にわたる受容と拒絶
第41章 医学・医療――COVID-19により世界に名を馳せた「新台湾医学」
第42章 少子高齢化と社会保障――遅れてやってきた福祉国家の課題
第43章 マスメディアとインターネット――抑制から多元化へ
Ⅳ 文化
第44章 文学――多言語多文化を包容する台湾文学
第45章 美術――台湾をいかに魅せるか
第46章 演劇――伝統と現代、それぞれの試み
第47章 映画――ニューシネマからエンタメへ
第48章 テレビドラマ――偶像劇ブームとポスト偶像劇
第49章 ポピュラー音楽――多様性が魅力の、台湾ポップスの歩み
第50章 文創――新旧共存する「台湾さがし」の受け皿
第51章 飲食文化――台湾美食の影に歴史あり
第52章 スポーツ――脱中国、グローバル化、そして台湾意識
第53章 中華文化・本土文化・日本文化――変わり続けた「正統」とその語り
第54章 宗教――越境とグローバル化
第55章 年中行事――台湾歳時記
第56章 家族・親族・宗族――親戚関係から見た台湾漢人社会
Ⅴ 対外関係
第57章 外政――外務・僑務・大陸事務
第58章 アメリカとの関係――同盟から保護へ 1949―2021
第59章 中国との関係――交流の拡大と新たな摩擦
第60章 香港との関係――冷え込む公的関係、強まる民間交流
第61章 東南アジアとの関係――南向政策を通じた実務外交の模索
第62章 日本との関係――切っても切れない重要な隣国
第63章 戦後処理と賠償問題――慰安婦、元日本兵
第64章 沖縄との関係――石垣島で土地公を拝む人たち
第65章 華僑と台僑――日本における中華民国/台湾の一側面
第66章 国際組織――国連脱退後の苦難と中国の圧力
第67章 安全保障――米中に翻弄され続ける台湾の防衛
【コラム6】兵役制度
Ⅵ 人物
第68章 政治――戒厳体制から民主化後まで
第69章 歴史――多様な背景の人物群像が織り成す400年間
第70章 経済――お金を動かす名家・実業家・IT企業家
第71章 文化――クロスオーバーが創り出す新たな価値
第72章 芸能とスポーツ――多様性ある社会、うつす鏡
参考文献
年表
執筆者一覧